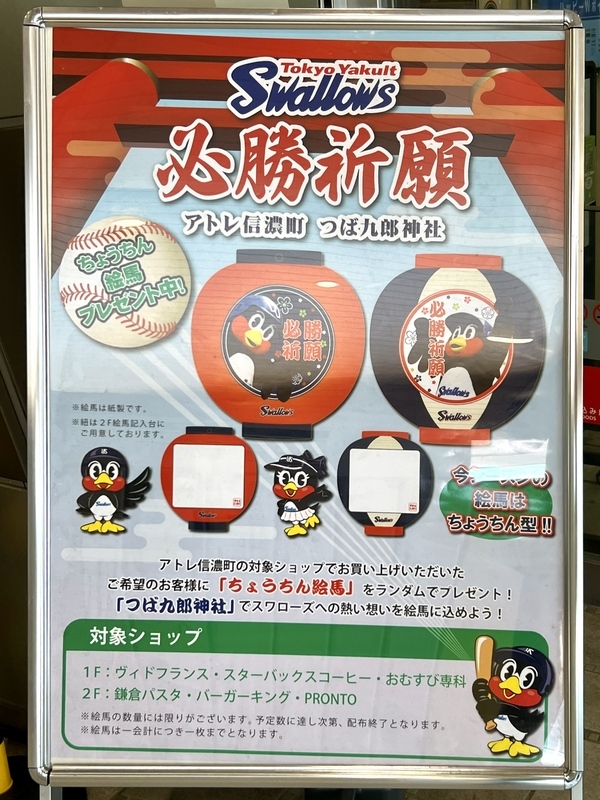はじめに

東京タワーは誰しもが知る日本の人気観光地だ。
個人旅行はもちろん、修学旅行で行ったという人も多いかもしれない。
更に国内のみならず、海外からの観光客も多数訪れている。

そんな東京タワーの足元、道路を挟んだ向かい側には、実は自然豊かな渓谷がある。
都立芝公園19号地


芝公園は明治6年(1873年)の太政官布告で造成された都内でもかなり古い公園だ*1。
その中でもこの場所は紅葉谷(もみじ谷)と呼ばれ、都立芝公園の19号地に当たる。

因みに明治43年(1910年)の『新編国民地図 』を見てみると、現在の東京タワーの位置には三縁亭という建物(料亭だろうか?)が建っており、ここも公園という扱いになっていたようだ*2。
石仏と蛇塚

園内に入ると、まず右側の階段に赤い帽子と前掛けの地蔵尊が並んでいるのが目に入る。


一番手前の石仏は赤い前掛けなので地蔵尊かと思ったが、像容からすると地蔵尊ではないのかもしれない。
この石仏には「元禄14年」と刻まれており、1701年の建立であることが分かる。
また前回訪れたときはこの石仏の右側に小さな大黒天像があったが、今回見ると無くなっていた。

手前から2番目は首飾りをかけられた地蔵尊だ。

さらにその隣も地蔵尊だろう。
手には数珠を握っている。

一番奥には蛇塚の入口を守護するように地蔵尊が立っている。

蛇塚の祠の中には龍神の像が鎮座している。
これは昭和40年(1965年)頃、新宿の飲み屋の女将が店に出た蛇を捕まえて紅葉谷に逃したところ店が繁盛したため、この場所に祠を建てて龍神像を祀ったことに始まるらしい*3。
大薩埵碑

観音堂前の道を更に進むと、左手に大薩埵碑がある。
大薩埵というと、道了大薩埵(大雄山最乗寺開山・了庵慧明禅師の弟子で、最乗寺創建に尽力した僧)のことだろうか。
【都立芝公園19号地】
住 所:東京都港区芝公園4-3-25
社祠等:蛇塚 外多数
H P:東京都公園協会HP「芝公園」